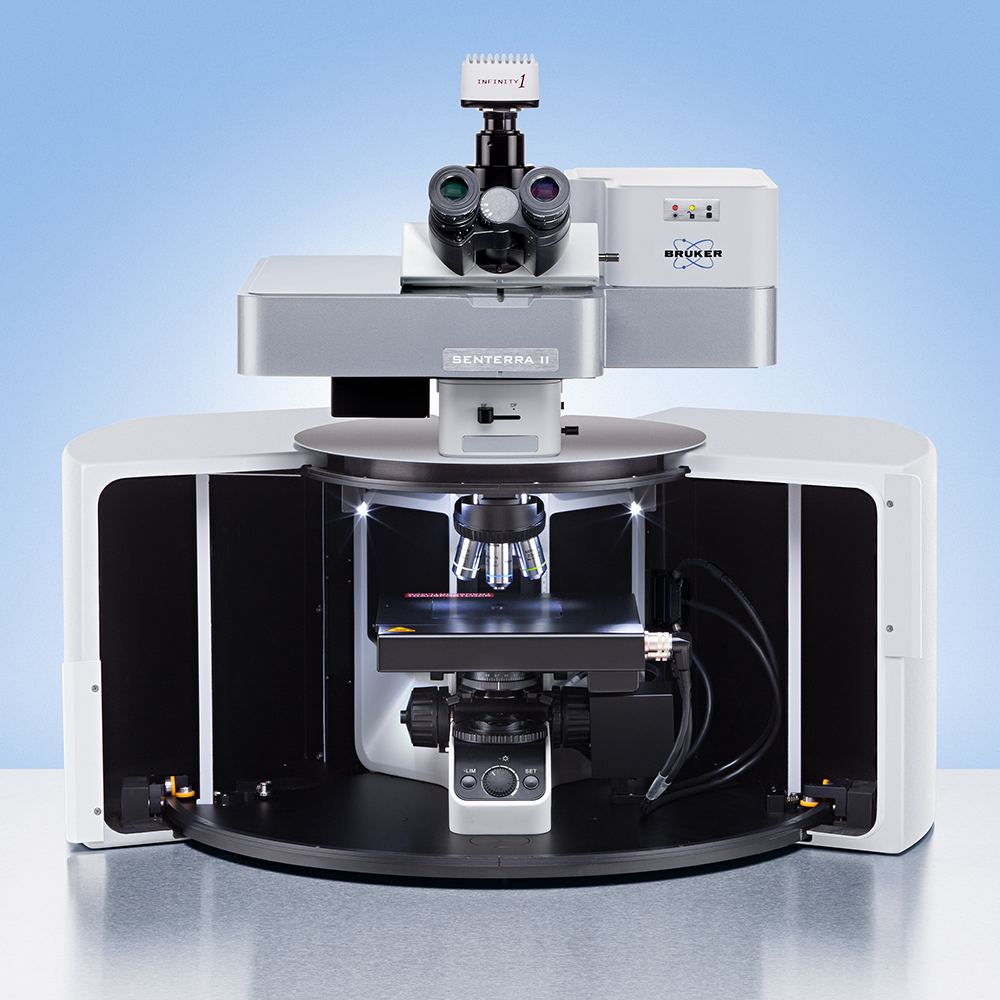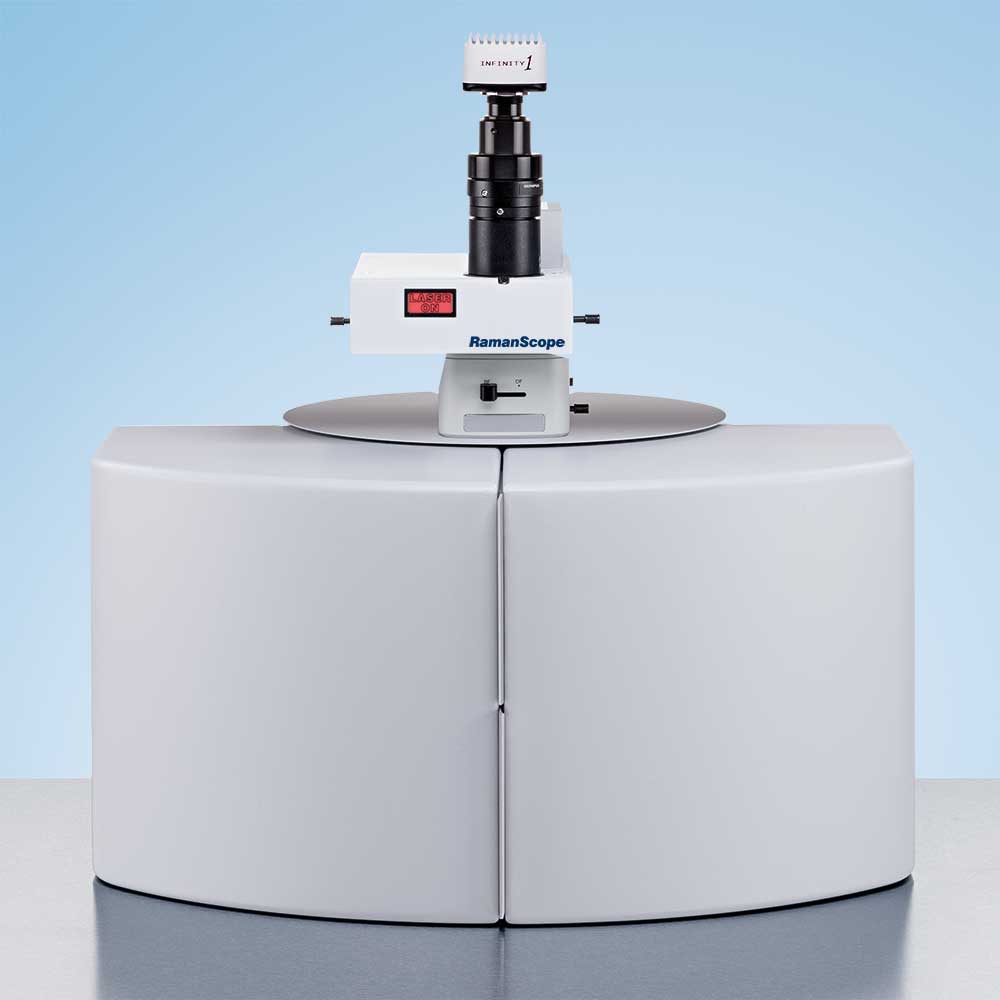最先端のラマン分光技術
ラマン分光法の改善
ラマン分光法には数多くのバリエーションがあり、試料の前処理がわずかに異なるだけのものもあれば、まったく新たな測定装置を必要とするものもあります。これらのバリエーションにより、ラマン分光法をより多くの試料へ適用することが可能となります。これらの代替技術は、通常、ラマン分光法のさまざまな制限に対処します。
表面増強ラマン分光法 (SERS) や先端増強ラマン分光法 (TERS) などの方法は、ラマン分光法の感度を高めることが可能です。FT-ラマンは、ラマン測定において妨害となる蛍光の抑制に有効です。これらの技術は、ラマン分光法の限界を克服するだけでなく、一部のアプリケーションでは従来のラマン分光法の能力を超えることさえ可能にします。
ラマン信号の増加
ラマン分光法の感度の向上に有効な技術はいくつかあります。これらの中には、ラマン分光計の特別なセットアップや変更が必要なものもあり、実行がより複雑になります。一方、試料の前処理の方法を少し変えるだけで、より強力な信号強度を得ることが可能な技術もあります。これらの技術によってラマン信号の強度を高めることで、DNAの一本鎖や個々の分子など、より小さな種を調べることができます。
表面増強ラマン分光法(SERS)
表面強化ラマン分光法は、実行が簡単で、試料の前処理をわずかに変えるだけで済むため、一般化されつつあるラマン技術の1つです。SERS は、通常、銀、金、またはアルミニウムでできているナノ粒子を含むガラス表面に試料を置くことによって効果が期待ができます。
最適なナノ粒子、そのサイズ、表面の厚さは各試料に固有のため、適切なセットアップを見つけるにはある程度の実験が必要です。ただし、測定に最適な表面が作成されると、ラマン信号の強度を最大10桁程度増やすことができます。
金属ナノ粒子を使用する代わりに、グラフェンの薄い層で同じ効果を得ることができます。この技術は、グラフェン強化ラマン分光法 (GERS) と呼ばれます。SERS と同様に、GERS はラマン信号の強度を大幅に向上させることができます。
先端拡張ラマン分光法(TERS)
先端拡張ラマン分光法(TERS)では、先端が非常に小さな探針 (10-50 nm) を使用して試料の表面を空間的にスキャンします。これにより、探針の先端付近に局在する非常に強いラマン信号が生成され、試料を非常に詳細に分析することが可能となります。これは、例えば、生体分子の分析や試料表面上の個々の原子の可視化に非常に有用です。しかし、この技術ではラマン分光計の改造が必要となるため、セットアップが非常に困難です。さらに、大型試料の研究には適していません。
ラマン分光法と組み合わせてラマン信号を増強できる手法は他にも数多くあります。そのため、実施する実験に応じて、これらの選択肢を検討してみる価値があるかもしれません。
FT-ラマン: 蛍光を防ぐ究極の方法
蛍光はラマンスペクトルの解析を妨害するため、ラマン分光測定では、蛍光の発生を防ぐことが重要です。そのためには、レーザーの波長を長くすることが有効で、一般には波長 785 nmのレーザーが用いられます。しかしながら、この波長でも蛍光を完全に除去するには不十分な場合もあります。
そのような場合、波長 1064 nmの近赤外レーザーを使用することで、より効率的に蛍光の発生を防ぐことが可能です。しかしながら、レーザーの波長を長くすると、ラマン散乱光の強度が低下します。特に分散型ラマン分光計では、回折格子を用いてラマン散乱光を波長分散させてCCDで検出しますが、CCD検出器は、長波長域においける感度が低くなりがちです。
これを改善する方法として、FT-IR や FT-NIR で用いられる干渉計の利用があります。つまり、1064 nmレーザーによる試料励起で発生したラマン散乱光を、回折格子ではなく、干渉計によって変調して記録する方法です。この場合、高感度な液体窒素冷却式ゲルマニウム検出器を用いることで、ラマン散乱光を効率的に検出することができます。
干渉計を用いると、回折格子で光を波長分散させる場合とは異なるデータセットが生成されます。ここでは、フーリエ変換と呼ばれる数学的演算を用いることで、干渉計の光路差を関数とするデータから、見慣れた波数を関数とするラマンスペクトルに変換することができます。この手法は、フーリエ変換がその技術の重要な役割を果たすことから、FT-ラマン分光法と呼ばれます。